車検のお役立ちコラム
2024年8月からヘッドライトの検査基準が厳格化される!その影響は?
- 公開日:

車検の検査項目の中で引っかかりやすいのがヘッドライトです。
ヘッドライトの検査は光量と光軸、そして色の基準をどれも満たす必要があり、いずれかが不良の場合には再検査が必要となります。そのヘッドライトの検査基準が2024年8月から厳格化されます。
ここではどういう部分が厳格化されるのか、それによってどんな影響があるのかをご説明します。

-
- 無料見積で必ずもらえる!!
- 目次
1.ヘッドライトの検査項目
ヘッドライト(前照灯)は夜間走行の際、車両前方の視界を確保するために存在しています。
それと同時に、対向車から見たとき眩しくないように調整されていなければなりません。では実際にはどんな検査がおこなわれているのでしょうか。
1-1.光軸
まず専用の検査機械で確認されるのが光軸です。これは対向車が眩しくないように光の配分が適正であるかどうかを確認する、という目的でおこなわれています。
具体的にはロービームを点灯したとき、上方向の光をカットする『カットライン』がはっきりと出ているかどうかが問題となります。
1-2.光量
光量は文字どおり、光が基準内の数値となっているかどうか、ということです。これも光軸と同じく専用の機器で計測されています。仮に基準値よりも暗い、という場合は車検にはとおりません。
1-3.色
ヘッドライトの色については『白色』であること、という基準となっています。一般的に白色というのは、ケルビン数でいうと3000〜7000kの範囲となるのですが、これについては検査当日、検査員が見て判断をします。
このケルビン数は数字が大きいと青色に、数字が小さいと黄色に見えますので、社外品のバルブに交換する場合は、おおよそ4500〜6500kの範囲としておくのが無難です。
2.基準の厳格化とは
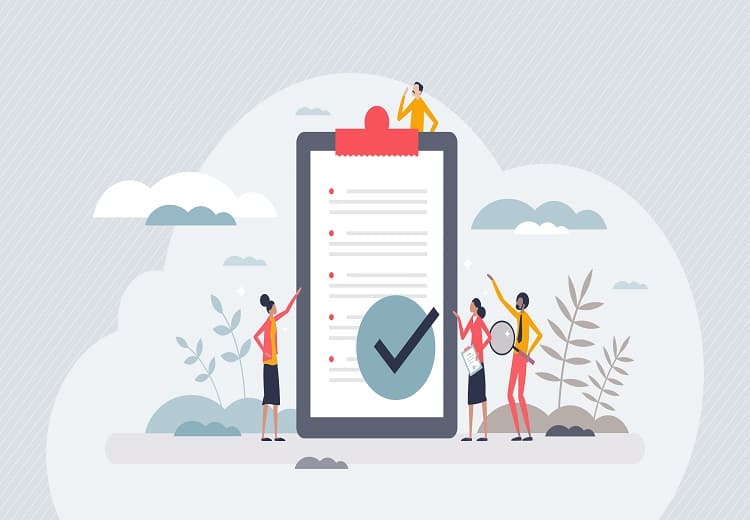
そんなヘッドライト検査の基準が厳格化されたというのは、どういうことなのでしょうか。
じつはヘッドライトの検査基準は、2015年に大きく変更されていて、2018年からはロービームで検査をする、ということになっていました。
ただ、その当時は旧基準で生産されていた車が多数走っていたこともあり、暫定措置としてハイビームでの計測でも基準に通過すれば問題なし、となっていたのです。
しかし2018年から5年以上が経過したことから、2024年8月からは本来の検査方法であるロービームで光軸と光量を計測する、ということが徹底されることとなりました。
この検査方法の対象となるのは、1998年9月1日以降に製作された自動車となっています。
3.基準の厳格化で起き得ることとは
では今回のヘッドライト検査基準の厳格化によって、どんな影響があるのかを考えてみましょう。
3-1.ヤングタイマー車への影響
まず大きな影響を受けるのは、1998年9月以降から2000年代初頭にかけて製造されたヤングタイマー車です。
この時代の車は、以前のガラス製ヘッドライトレンズから樹脂製ヘッドライトレンズへと変わった世代です。このころの樹脂製ヘッドライトレンズは表面のコーティングがまだ完成されておらず、ほうっておくと黄ばんでしまいがち。そうすると光量が落ちてしまうため、そのままでは基準を満たすのが難しくなります。
そこでレンズ表面を磨いて再コーティングをする、という作業が必要となるのですが、古い車の場合にはヘッドライト灯体内部のメッキがくすんでしまっていることも多く、いくらレンズ表面を磨いてきれいにしても光量不足が解消できない、ということが実際に起きています。
そのため、とくに部品が欠品しがちな輸入車では、状態のいい中古ヘッドライトの価格高騰がすでに起きている、というのが現状です。
部品供給が比較的おこなわれやすい国産車でも、車種によっては中古ヘッドライトの価格が値上がりしています。また、ヘッドライトを分解(から割り)し、内部を再メッキしてくれる修繕業者も増えてきています。
そのため今後は、2000年代初頭に新車登録された車の車検費用が、ヘッドライトのパーツ代のぶん高くなることが考えられます。
ちなみに輸入車の場合、右側通行左ハンドル車用のヘッドライトは、社外品も含めて部品供給は比較的潤沢です。
ただ、この左ハンドル用ヘッドライトはカットラインが右側通行用となっているため、日本の左側通行用カットラインとは合致しません。きれいなヘッドライトがないからといって、左ハンドル用ヘッドライトを購入してしまうと無駄遣いとなる可能性が大きいのでご注意ください。
3-2.メンテナンスしたらかえって通らなくなることも?
ヘッドライトの表面がきれいな最近の車でも、ヘッドライトの検査が不合格となることがあります。
たとえばHIDヘッドライトの車で、光の元であるバーナーが点灯しなくなったために社外品のバーナーへと交換したという場合、光点の位置が微妙にずれてしまったためにカットラインのエルボー点(左側の歩行者を照らすための左上がりカットラインの開始点)がぼやけてしまった、ということも起こりえます。
実際筆者が所有している中古車で購入したトヨタ・ヴィッツも、前回の車検でエルボー点がはっきり出ておらず、再検査となりました。
これはロービームでの検査でもっとも引っかかりやすい部分です。
車検対応品と銘打たれているアイテムであっても、純正バーナーと光点位置がまったく同じであるかどうかは装着して検査をしてみなければわかりません。さらにHIDよりもさらに明るいLEDバルブへ交換している場合なども、光点位置の違いからカットライン不良で再検査となる例が多いようです。
4.まとめ
ヘッドライトの検査基準が厳格化されることによって、ヤングタイマー車は車検にとおらない、という可能性がささやかれています。
仮にヘッドライトのレンズを磨いて再コーティングし、灯体はから割りして内部のメッキをやり直してそのときの車検はとおったとしても、水分は元のヘッドライトと比べれば確実に進入しやすくなるため、内部の劣化は以前よりも早く進行することになるでしょう。そのコストを毎回の車検でかけてまでヤングタイマー車を持ち続ける人がどれほどいるのでしょうか。
またヘッドライトの交換で対処をしようと思っても、中古パーツは枯渇していくため価格高騰は続くでしょうし、新品パーツの供給は自動車メーカーが決断をしない限りほぼあり得ません。
そのためとくに輸入車ディーラーや、輸入車を専門としている整備業者の間では、お客様になるべく迷惑をかけないよう、なるべく状態のいい中古ヘッドライトを在庫しておく、という動きがすでにはじまっています。筆者が所有しているもう1台のヨーロッパ車も、すでに1セット、中古ですが状態のいいヘッドライトを用意していて、次回の車検時にはそれを装着する予定です。
国産車の場合には、販売台数が多いこともあって現状中古ヘッドライトの価格は大きくは動いていませんが、今後どうなってくるのかはわかりません。販売台数が多いということは、それだけ車検を受ける車も多いということですので、あまりに多くの車が検査に通らないということになると、ユーザーだけではなく整備業者やディーラーからの、国土交通省に対する苦情も増えるはずです。可能性にすぎませんが、そうなったときには、検査基準の緩和、ということがあるのかもしれません。
いずれにしても現状では、2024年8月からロービームのみでの光軸、光量、色の検査がはじまるということになっています。そのためそれ以降の車検が予定されている場合には、いまからでもしっかりと対策しておくことをおすすめします。
- この記事の執筆者
-
- 自動車専門ライター 高田 林太郎
- 自動車雑誌の編集者として出版社に勤務したのちフリーランスライターとして独立。国産・輸入車の紹介からカスタマイズ、自動車周辺企業への取材など、自動車業界の現場にてさまざまに活動中。


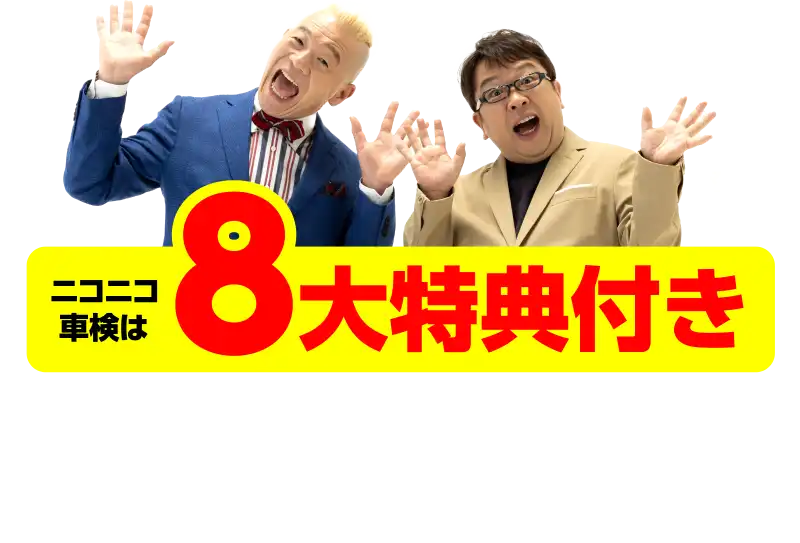

【8.オイル交換無料について】当店選定のオイルになります。またディーゼル車の場合、別途費用が発生します。